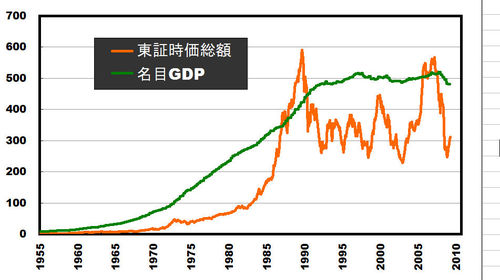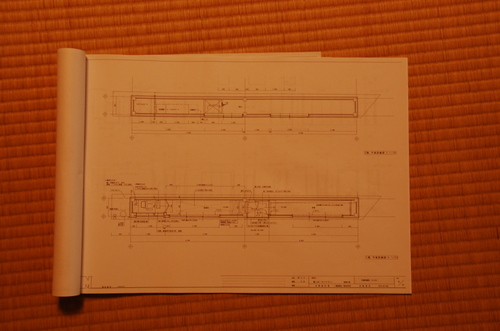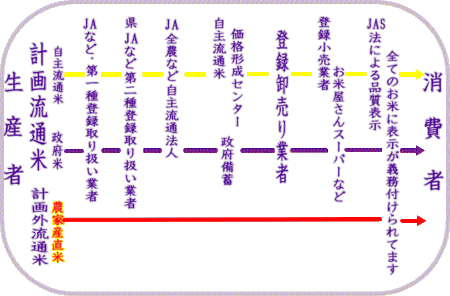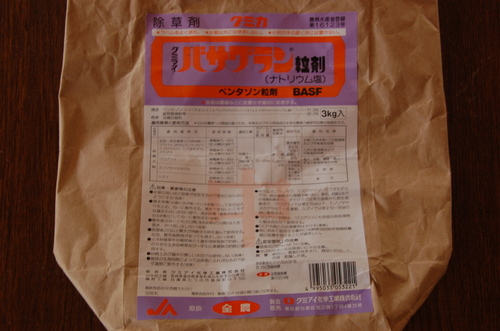2009-08-18
昼の田んぼ道
カテゴリー: 4 記録 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-08-17
犬山
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-08-16
朝の田んぼ道
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-08-14
琵琶湖
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-08-13
2009-08-11
テニス屋 8
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
テニス屋 7
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-08-10
田んぼ 4
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
テニス屋 6
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-08-09
米花
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-08-08
坂本
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-08-07
テニス屋 5
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-08-06
パタパタロック
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-08-05
日吉大社
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-08-04
テニス屋 4
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-08-03
先生の田畑
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-08-02
花火大会
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-08-01
七輪
カテゴリー: 4 記録 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-31
田んぼ 3
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-30
穂
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-29
2009-07-28
テニス屋 3
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-27
テニス屋 2
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-26
ヤモリ
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-25
農家直配卵
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-24
2009-07-23
水田
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-22
天災 下
カテゴリー: 4 記録 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-21
天災 上
カテゴリー: 4 記録 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-20
ヨット 下
カテゴリー: 1 ヨットと山 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-19
ヨット 中
カテゴリー: 1 ヨットと山 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-18
ヨット 上
カテゴリー: 1 ヨットと山 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-17
水田 After
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-16
水田 Before
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-15
無題
七月十五日、送り火。
ご先祖様が、あの世に無事帰れるよう、家の前で送り火を焚きました。
おっさまが、盆とはご先祖様に感謝をすることだとおっしゃいました。
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-14
テニス屋 1
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-13
無題
七月十三日、迎え火。
ご先祖様が、家に迷われぬよう、家の前で迎え火を焚きました。
仏壇の前に位牌を並べて、ご馳走をおいて、おっさまが来られる。
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-12
川上り
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-11
田んぼ 2
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-10
坂本
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-09
比叡山坂本
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-08
芦屋
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-07
近江八幡
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-06
マンション
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-05
ホタル
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-04
近江八幡
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2009-07-03
除草剤
| 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
アバウト
カテゴリー
- GREEN SQUARE (工場を住宅に模様替え) 1009→1205 (21)
- re + house (リフォーム) 1112→1209 (11)
- WGP FACTORY (工場2,500㎡) 1006→1105 (7)
- 世代を繋ぐ庭 (木造平屋) 1201→ (12)
- 八百津の家 (住宅) 1108→ (14)
- 妹たちのいえ (30坪の小さな家) 1105→1112 (20)
- 設計 (いろんな現場) 1004→ (37)
- 農家の再生 (季節を知る) 1103→ なし (3)
- 1 ヨットと山 (21)
- 2 野良 (58)
- 3 自宅 (43)
- 4 記録 (64)
- 5 サロン (29)
- 6 子供 (24)
- 7 news (5)
- 8 休日 (20)
- 9 建築 (28)